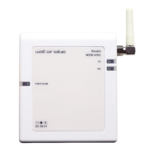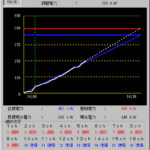表面温度計測は目的によって施工方法が異なります。
また、表面温度は正確な計測が比較的難しいことをご理解の上、計測を行ってください。
配管表面温度の計測
施工上の理由により配管内に挿入することが困難な場合に、やむをえず配管表面温度を計測し内部流体温度とすることがあります。その場合は配管とセンサーを密着させて動かないように固定し、その上から保温材で覆い、配管とセンサーを一体化し、同じ雰囲気下に置くことが重要です。保温材内部の空隙(くうげき)はシリコングリス等で埋めると更に効果的です。
この方法で施工した場合、ある程度正確な計測は出来ますが、この温度はあくまでも配管表面の温度であり、配管内流体温度では無いことをご理解ください。
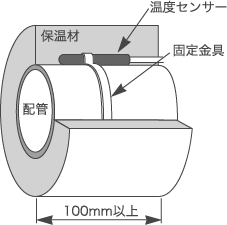
個体表面温度の計測
測定したい固体の表面に温度センサーを密着させます。
その際に周囲からの熱影響をなるべく少なくするためにできる限り長く沿わせ、密着する面積を大きくします。周囲温度が高温の場合には輻射(ふくしゃ)熱に影響されないよう、断熱カバーを取り付けます。
もっと正確に表面温度を計測するには、固体表面に溝を作り、その溝の中に温度センサーを沿わせるようにし、固体の表面付近に埋め込むようにします。
また、固体表面付近に固体表面と平行に深い穴が開けられる場合は、その穴にセンサーを挿入することも有効な策です。
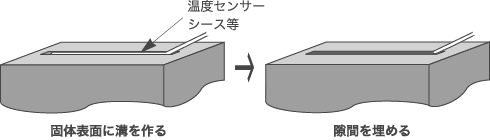
表面温度計測時の温度センサーの選定
配管表面温度の計測や固体表面温度の計測でも、温度センサーを密着させることができ、ある程度の長さを沿わせることができる場合は、元々の精度が高い測温抵抗体を使用することが多くあります。
しかし、狭小表面の温度を計測したい場合は熱電対を使用した方が良好な結果が得られる場合もあります。これは測温抵抗体と熱電対の測温部の大きさによるもので、測温抵抗体は一定の抵抗を作り出すために、素子内部で抵抗線が巻いてあったり、基板上に白金膜が形成されているため、ある程度の大きさがあり狭小表面の温度計測には向きません。
それに対し熱電対は+素線と-素線を溶接した温接点一点が測温部となるため、狭小表面では有利になります。但し、下図に示す通り温接点のみを接触させただけでは、温度センサーの吸熱よりも放熱の方が大きくなってしまい測定誤差が生まれます。
そこで通常は線状になっている熱電対素線を薄板状にし、接触面積を増やすことで吸熱効果をあげることができる熱電対も市販されています。
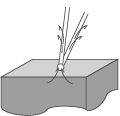
吸熱<放熱
点で接触するため測定誤差が一番大きい
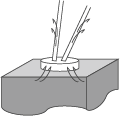
吸熱<放熱
プレートを設け吸熱面積を大きくしているが放熱も大きい
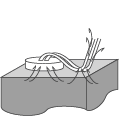
吸熱<放熱
熱電対を固体表面に沿わせ放熱を制限
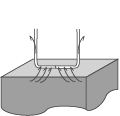
吸熱≒放熱
接触面積が大きく放熱が極めて少ない
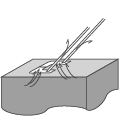
吸熱≒放熱
薄板状の熱電対で吸熱面積が大きい