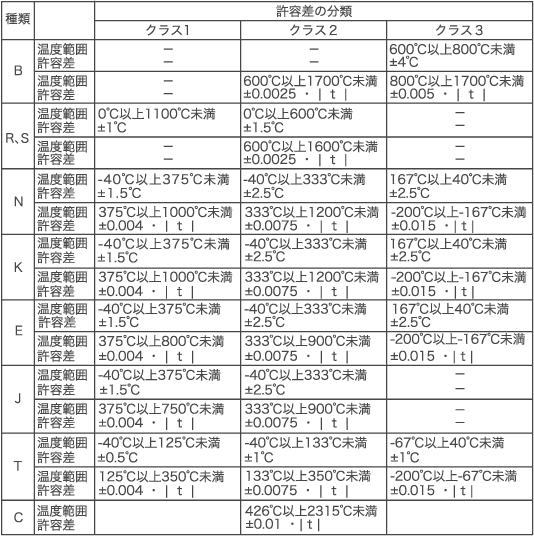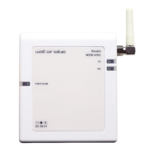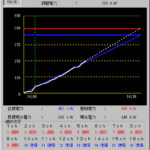熱電対は2種類の異種金属の一端を溶接したもので、温度変化と一定の関係にある熱起電力を利用して温度を測定するセンサーです。
熱電対の原理
2種類の金属(A、B)を接触させると電子の移動によって接触部に電位差が生じます。図1のように閉回路にすると、2つの接点の温度(T1、T2)が等しい場合は両方の電位差が相殺して電流が流れませんが、片方の接点の温度(T1)を上げると不均衡が生じて電流が流れ、温度(T1、T2)による起電力の差が「熱起電力」となります※。
熱起電力の大きさは2つの金属の種類と両接点の温度によって決まり、金属の形状や大きさには無関係です。
従って、2つの金属の種類と熱起電力の大きさ、および片側の接点の温度(T2)が分かっていれば、もう片方の接点の温度(T1)を知ることができます。これが熱電対の原理で温度を測る側の接点を測温接点、または温接点、基準にする側の接点を「基準接点(冷接点)」と言っています。
基準接点温度(T2)が0℃の時、熱電対の種類別に測温接点の温度(T1)に対応した熱起電力の値が規準熱起電力表として日本工業規格「JIS C 1602」で規定されています。
熱電対を温度センサーとして使用する際には、測温接点側を測定場所の基準接点側を電圧計に接続する必要があります(図2)。ただし、その場合基準接点側が一定の温度にならないため、基準接点となる部分を氷水の中に入れて0℃に保つか、温度補償回路が内蔵された計測機器を使用します。
※ 同現象は、発見者の名を取って「ゼーベック効果」と呼ばれる
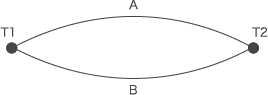
図1 熱電対回路
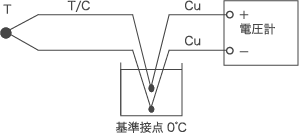
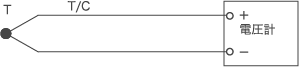
図2 熱電対と基準接点
熱電対の特長
熱電対は温度計測のあらゆる分野で最も多く使用されている温度センサーで、多くの優れた特長があります。
◇熱起電力として熱電対自体が出力信号を出します。
◇構造がシンプルなため耐久性に優れ、比較的安価です。
◇極低温から超高温まで広範囲の温度測定ができます。
◇細径の製造ができるので、小物体、狭小空間の温度測定が可能です。
◇感温部が小さいため応答性に優れます。
ただし、熱電対には下記のような短所もあります。
◇精度が測定温度の±0.2%程度と高精度な測定はできません。
◇基準接点補償が必要で、熱電対と計測機器の間は補償導線を使う必要があります。
◇測定雰囲気によっては熱電対の種類に制約があります。
熱電対の種類
JIS C 1602では熱電対の種類としてB、R、S、N、K、E、J、T、Cの9種類が規定されています。各熱電対はそれぞれに特長がありますので使用環境に合ったタイプを選択してください。
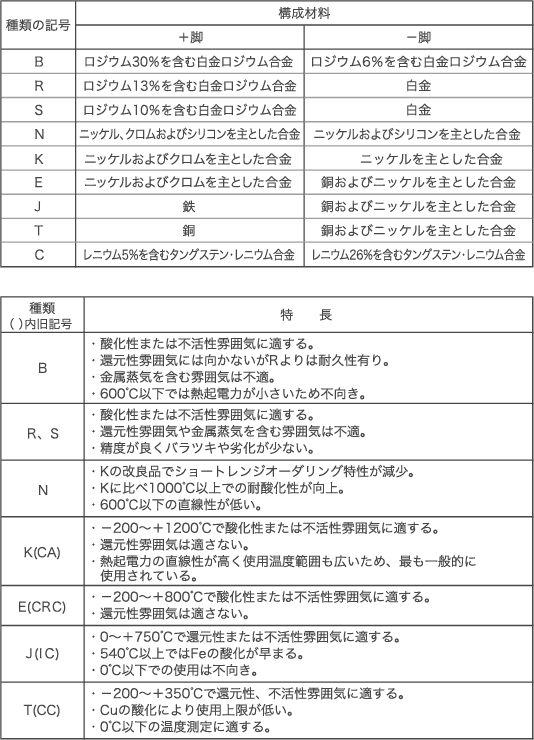
熱電対の許容差
JIS C 1602では各熱電対の許容差としてクラス1、2、3の3種類を規定しています。