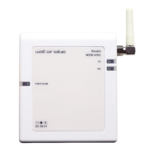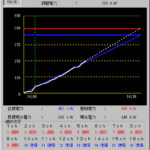測温抵抗体の計測誤差原因は、自己加熱や絶縁抵抗の低下など、様々な原因が考えられますが、適切な構造、適切な使用方法で誤差を軽減することができます。
自己加熱による誤差
測温抵抗体は抵抗素子に電流を流して温度を測定するため、その電流が微弱でも抵抗素子自体が発熱をし、実際の測定対象よりも若干高い温度を示します。これを自己加熱と言います。JIS C 1604 – 1997 では規定電流を0.5mA、1mA、2mAのいずれかと規定しており、製品はいずれかの規定電流に合わせて精度保証をしています。
一般的には測温抵抗体、受信計器で規定された規定電流以下で使用することが必要です。例として、弊社製品に多く使用している抵抗素子の自己加熱による誤差を下記に示します。
抵抗素子の自己加熱による温度誤差は次式により計算できます。
ΔT=I2×R×S×103
ΔT:自己加熱による温度誤差(℃)
I:通電電流(A)
R:抵抗値(Ω)
S:自己加熱係数(K/mW)
(注)弊社製品に多く使用しているセラミック巻線型抵抗素子の自己加熱係数は0.08K/mW(風速1m/sにおいて)です
1mA用として製作された素子をほかの規定電流で使用した場合の自己加熱による温度誤差は表の通りになります。
(注)表の値は1mAの時の温度誤差(調整済み)分を差し引いた値
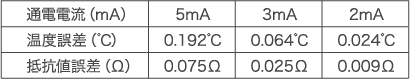
絶縁抵抗の低下による誤差
測温抵抗体は設置雰囲気の影響(多湿環境等)や絶縁材の経年劣化、製造時の水分の侵入などにより、使用中に絶縁抵抗が低下することがあります。その低下の度合いにより温度測定に誤差を生じる場合や、温度計測が不可能になる場合もあります。
例えば、計測温度が100℃のとき、絶縁抵抗が10MΩであればその温度誤差は0.005℃程度であり、温度計測上問題がない範囲ですが、絶縁抵抗が1MΩまで低下するとその温度誤差は0.05℃まで上がり、測温抵抗体の精度に大きく影響してきます。絶縁抵抗の低下を最小限に抑えるためには、保護管内と外気とを十分に遮断できる構造にすることが必要です。
経年劣化による誤差
測温抵抗体を使用していると下記の要因等により経年劣化が起き、温度測定に誤差が生じる可能性があります。
- 通電電流による自己加熱の影響
※自己発熱により抵抗素子内部の白金線表面の酸化が起こり、白金線が細り抵抗値が大きくなる傾向があります。 - 測定対象の温度変化による熱衝撃の影響
※白金線が塑性(そせい)変形を起こし、抵抗値が変化します。 - 振動、衝撃の繰り返しによる影響
※白金線が塑性(そせい)変形を起こし、抵抗値が変化します。さらに、白金線を固定している接着剤が剥げ落ちて、コイル状に巻かれている白金線が互いに接触することにより抵抗値が小さくなる傾向があります。 - 異常電圧、電流(落雷、高圧放電等)による影響
※(1)と同じような現象が急激に起きますが、ほとんどの場合、瞬間的に断線に至ります。このような経年劣化による誤差が生じた場合は、一般的には製品寿命であると考えられますので、交換することが望ましいです。
白金測温抵抗体の許容差
JIS C 1604 – 1997 ではクラスA、クラスBの2種類の許容差が規定されています。
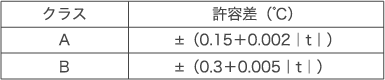
(注)|t|:+、-の記号に無関係な温度(℃)で示される測定温度